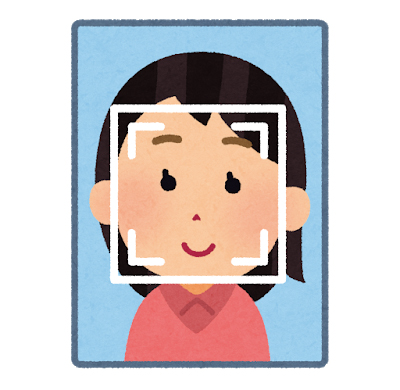医学+AIで脳卒中の早期発見に挑む

生活習慣病に起因する病気の一つとして知られる、脳卒中。年間に33万人が脳卒中で救急搬送されており、平均すると1日1000人、2分に1人搬送されている。実は、脳卒中には有効な薬が存在するにもかかわらず、早期発見の遅れからほとんど投与されてない現実がある。大学で学ぶ学問と、身近な人の脳卒中をきっかけに、これらの課題解決の事業プランを考えたのが、高畑氏を代表として、医学部医学科5年の大前氏(写真左 )と、医学部看護学科4年の長尾氏(写真右)が結成した、チームQual+IA(クオリア)だ。
有効な治療法の普及を阻む「時間」の課題
脳卒中はほどんど前兆がなく、前日に医師が診察していても、予測することができない。つまり、発症してから治療することになるが、実はそこに「時間」という大きな課題がある。「発症」→「発見・連絡」→「搬送・診断」→「治療」という大きく4つのフローがあり、治療においては、「tPA血栓溶解療法」という非常に有効な方法が知られている。しかし、発症後「4.5時間」以内にしか使えないため、普及していないという課題がある。代表の高畑氏は「119番通報されてから病院で治療を開始するまでの平均が2時間です。しかし、フロー全体で『10時間』かかっているという報告もあり、発症してから発見されるまでの時間が2.5時間を大きく超えている実態が見えてきたのです」と言う。
スマホアプリで発症を検知
起床から就寝まで、常に覗き込むスマートフォン。最近では顔認識でロック解除する機能も普及してきた。高畑氏は「脳卒中の初期症状である、顔面の片麻痺を検出できるのではないか」と想起し、同大学内で、ロボット開発やプログラミングに長けた仲間を募った。そして、画像認識でよく使われる深層学習手法「CNN」を用いたプロトタイプ開発へ取り組んだ。その結果、実際にWeb上から「顔面麻痺、正常ともに120枚ずつ」を用意し、精度「90%」と高い値が得られるようになったのだ。また脳卒中は、一度発症すると10年以内の再発率が50%を超えており、本人だけでなく周囲の家族も、日々の生活に大きな不安を抱えることになる。常時顔認識するアプリが与える安心感はとても大きいだろう。彼らは、「文部科学省 次世代アントレプレナー育成事業 (EDGE-NEXT)」の採択を受けている滋賀医科大学が主宰するピッチコンテストや滋賀テックプラングランプリなど、いくつかのビジネスプランコンテストにも参加し、積極的に事業プランのブラッシュアップに取り組んだ。
事業化へ向けて、研究、進学を着実に進める
グランプリ後の2019年8月には、科学技術振興機構(JST)の大学発新産業創出プログラム「SCORE」に採択され500万円の研究開発費を獲得した。現在は、脳卒中の治療や研究に従事している日本脳卒中学会の幹事である滋賀医科大学脳神経科学講座の野崎教授の協力のもと、顔面麻痺のある患者のデータを収集する臨床研究を、学内倫理委員会承認を得て進めている。受賞後のパートナー企業との話し合いの中から、大学と企業間の協定が締結されるなど、学生に端を発する活動が、県内の新しい産業創出エコシステムにも発展しはじめた。今後は、連携へ向けた話し合いも本格化する予定だ。チームメンバーらは、2020年、2021年に研修医、大学院進学を予定しており、医師と事業の両立を目指している。医療の現場を知る医学生だからこそ生まれた事業プランが、いつか多くの人の命を救い、安心をもたらすかもしれない。
滋賀テックプランター vol.04 (2020年4月 発刊)